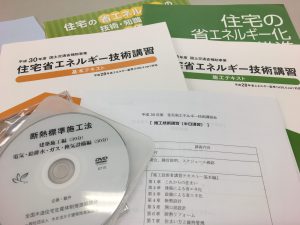江戸には町火消はいろは四十八組あるそうです。
そのほかに、練馬、板橋や北、足立エリアなどの組が加わってかなりの組数になっていますね。

結果、四十八組のほかに数組ありそれぞれが一番から十番くらいまでの纏を継承しているので全部では百くらいの纏が並んでました。
かつ、それぞれの組で梯子のり担当、纏担当、差又担当、とりまき、頭集などがいますから会場には概ね四百人くらいはいたのではないかと思います。

壮絶でした!
神輿も凄いけど、町火消しも凄いです。
次世代に繋いでいく文化と思います。
ところで、消防団と町火消しは少し違います。
消防団には誰でも入れますが、町火消しは『鳶』さんでなければ入れないそうです。
鳶=頭(かしら)はご存知ですか?
仲間の鳶さんから聞いた話で真偽のほどはわかりませんが、
鳶=高いところにのぼる=全体を見渡す=町内のことは把握している=頭・・・なのだそうです!
江戸は『鳶=頭』ですが、関西の『鳶』さんは何というのでしょうね?(笑)
町火消しは江戸から三百年の歴史があるそうです。
やはり江戸っ子の組頭も埼玉県や千葉県に住んで、組を守っているそうです!時代には勝てないようです。
目次